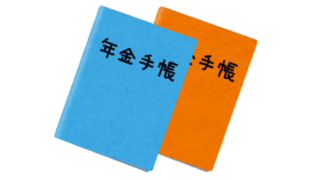離婚公正証書を作るとき『交付送達』は必要? メリットをしっかり解説

夫との離婚に際して公正証書の作成を準備していますが、公証役場から「交付送達を希望しますか」と聞かれました。これはどういう意味でしょうか?

将来、養育費などの支払いが滞った場合に、強制執行できることが、公正証書作成の大きなメリットです。その強制執行の手続の一部を、あらかじめ作成当日に済ませておくのが『交付送達』です。
わかりやすく説明しますね。
- この記事では、「夫が妻に養育費を支払う」ケースを例に説明します。典型的な例を挙げるもので、他意はありませんのでご理解ください。
そもそも『交付送達』とは?
離婚公正証書を作成するとき、公証人から「交付送達をしますか?」と聞かれることがあります。
この『交付送達』とは、公正証書を作成したその場で、相手方にも正式に 謄本を交付し、「この文書を確かに受け取りました」という事実を公的に証明する手続のことです。
なお、協議離婚における公正証書の作成について迷っておられる方はこちらの記事『離婚の手続って離婚届の提出だけ?』を一読してみてください。
『送達』とは?
法律上の『送達』とは、書類を相手方に正式に届けたことを証明する制度です。
例え公正証書を作成したとしても、強制執行を行うには「その内容が相手に正式に届いた」ことを証明する必要があります。
その証明書が『送達証明書』です。
『交付送達』は特別なタイミングで行う送達
通常の送達は、公正証書作成後に郵便で行う『特別送達』ですが、『交付送達』は、作成当日に当事者が揃っている場で手渡しで完了させる送達を指します。
公証人が立ち会いのもとで公正証書を交付し、受領の記録を残すため、確実性が高いのが特徴です。
作成当日に交付送達を行えば、同日付で『送達証明書』が発行できるため、将来の強制執行をスムーズに進めることができます。
交付送達のイメージ
- 公正証書の作成日、夫婦双方が公証役場に出向く
- 公正証書の内容を確認し、『原本』に双方が署名する
- 夫が公正証書の『謄本』を、妻が執行に使用できる『正本』を受取る
- 妻が、交付の事実を記録した『送達証明書』を受け取る
この手続により、「相手 (夫) が公正証書を正式に受け取った」という事実が公的に確定します。この『送達証明書』が、将来の強制執行に必要となる重要な書類です。
なお、交付送達を行った場合でも、相手 (夫) には『謄本』でなく『正本』 (交付用) が渡されるケースもあるようです。
(ご参考) 公正証書の電子化
電子公正証書制度の導入により、2025年10月から順次、公正証書がデジタル化が進められています。
原本は電子的に保管され、正本・謄本は従来通りの紙媒体でも、電子データ (PDF形式) でも発行可能です。
交付送達を行った事実も電子的に記録され、従来通りに『送達証明書』が発行されます。
また、署名押印に代わり、デジタルペンによる電子署名などで本人確認が行われます。
『強制執行』とは?
前章で説明した『交付送達』が、なぜ重要なのか――それは『強制執行』の仕組みと関わっています。
強制執行とは、相手が約束を守らない場合に、裁判所の力を借りて支払いや財産の引き渡しを強制する制度です。
簡単に言えば、「払ってくれないなら、裁判所が代わりに取り立てる」という手続です。
たとえば離婚後、夫が養育費を支払わなくなった場合――
妻 (債権者) は裁判所に申立をして、夫 (債務者) の給与や預金口座などを差し押さえることができます。
このように、強制執行は “約束を実現させる最後の手段” と言えます。
公正証書を作成する意義
通常の契約であれば、相手が支払わない場合にすぐ差押えを行うことはできません。
まず裁判を起こし、「あなたはこのお金を支払う義務があります」と認める判決 (『債務名義』に該当します) を得る必要があります。
ところが、公正証書の場合は少し違います。
もしその中に次のような一文が入っていれば――
支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服することを認諾します。
この一文 (=強制執行認諾文言) によって、公正証書そのものが判決と同じ効力を持つことになります。
つまり、裁判をしなくても差押えに進める、というわけです。
離婚公正証書における『強制執行認諾文言』は、養育費・慰謝料・財産分与など金銭の支払い条項に広く使われています。
強制執行の手続の流れ
実際に養育費などの支払いが滞ったとき、どのように強制執行が進むのかを見ておきましょう。
- 送達証明書を取得する
相手 (元夫) に公正証書を正式に届けます。
この手続を『送達』と言い、送達が完了したことを証明するのが『送達証明書』です。
※ 公正証書作成時に『交付送達』をしておけば、この段階はすでに完了しています。 - 戸籍謄本を取得する
公正証書を離婚前に作成した場合のみ、離婚成立を確認できる戸籍謄本が必要になります。離婚の成立が公正証書の効果を発生させる条件となるためです。 - 公正証書の正本を準備する
公証役場で作成したときに受け取った公正証書の『正本』を用意します。 - 公証役場で執行文の付与を受ける
公証役場で❶〜❸を提出して、公正証書の正本に
「この文書に基づいて強制執行できる」
という執行文を追記してもらいます。これにより公正証書が強制執行力を持つ正式な『債務名義』になります。 - 地方裁判所に強制執行を申立てる
上記の『送達証明書』、『戸籍謄本』、『執行文付き公正証書』を添えて、地方裁判所に強制執行を申し立てます。
それに基づき、裁判所が差押命令を発令します。 - 未払金を受取る
差押命令が勤務先や銀行に送達されると、差押対象のお金 (給与・預金など) が債権者 (元妻) に支払われます。
このように、公正証書を作成しておけば、裁判を経ずに直接、財産の差押えまで進めることが可能です。
さらに、交付送達を行っておくと、最初の『❶ 送達証明書取得』の工程を省略でき、執行までの期間を大幅に短縮できます。
『交付送達』をしておくメリット
強制執行の手続の流れの中で、実は最も時間がかかるのが『❶ 送達証明書の取得』です。
公正証書を相手に送達 (正式に届ける) するには、通常は『特別送達』といって、郵便で送る方法をとります。
しかし、相手が転居していたり、受取を拒否したりすると、再送や補充送達が必要になり、数週間から数ヶ月も余分にかかる恐れがあります。
そこで役立つのが『交付送達』です。
作成当日に公証人立会いのもとで相手に公正証書を交付しておけば、その時点で送達が完了し、同日付で『送達証明書』が発行できます。
つまり、将来もし不払いが起きても、
「執行文の付与」→「差押申立て」
へと、すぐに進めることができるのです。
もちろん、手続の迅速さが、結果として回収の実効性にもつながります。
離婚前に作成した公正証書でも意味はあるの?
公証役場では、ときどき「離婚前だから交付送達をしても意味がないですよ」と言われることがあります。
確かに、離婚がまだ成立していない段階では、
「支払義務の条件 (=離婚の成立)」
が満たされていないため、すぐに強制執行はできません。
しかし、これは “今すぐ執行できない” というだけで、交付送達そのものが無効になるわけではありません。
むしろ、離婚成立後に執行文を付ける際には、すでに『送達証明書』が手元にあるため、書類がそろい次第、即日で『執行分の付与』に移れるという大きなメリットがあります。
つまり、交付送達は “いざというときの準備” を、前もって完了しておく行為なのです。
交付送達の有無による強制執行の流れの比較
交付送達をした場合としない場合では、実務上どのような差が生じるでしょうか。
| 手続の流れ | 交付送達なし | 交付送達あり |
|---|---|---|
| 送達証明書の取得 | 特別送達を実施 (数週間から数ヶ月) | 公正証書作成当日に完了 (=交付送達) |
| 執行文の付与 | 送達完了を待って、その他の書類収集後に申請可能 | 書類収集後すぐに申請可能 |
| 差押命令の申立 | 執行文付与後に申立可能 | 執行文付与後に申立可能(左に比べて準備期間が短い) |
このように、交付送達をしておくかどうかで、将来の強制執行のスピードと確実性が大きく変わります。
まとめ
公正証書を作成する目的は、将来のトラブルを防ぎ、安心を確保することにあります。
その中で『交付送達』は、万一の不払いの際に、迅速に強制執行に進めるための “予防的な手続” です。
もちろん、交付送達をしなくても公正証書自体は有効に成立します。
ただし、離婚後に相手が転居したり、連絡が取れなくなった場合には、送達証明書の取得に時間がかかることがあります。
公正証書の作成当日に交付送達を済ませておけば、万一の際の強制執行に向けた手続がひとつ省略できます。
手数料は 2,000円ほどかかりますが、安心料としての価値は十分にあるでしょう。
なお、養育費を確保する手段としては、民間の『養育費保証サービス』を選択肢としても良いでしょう (詳しくはこちらの記事を参照してください)。
離婚後の安心をどう設計するか...
ぜひ一緒に考えさせてください。
お気軽にお問合せください
折り返し、お電話またはメールにてご連絡させていただきます。